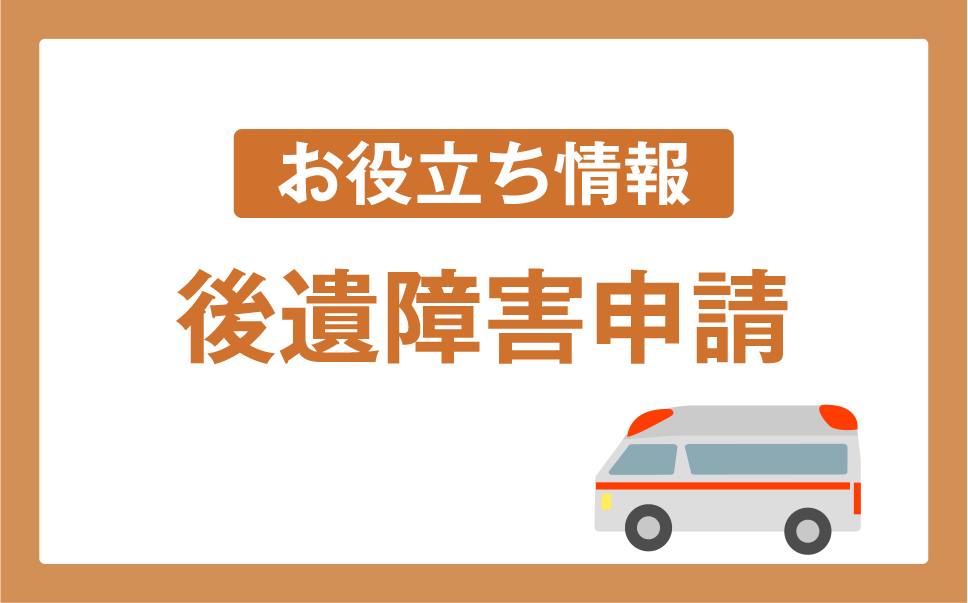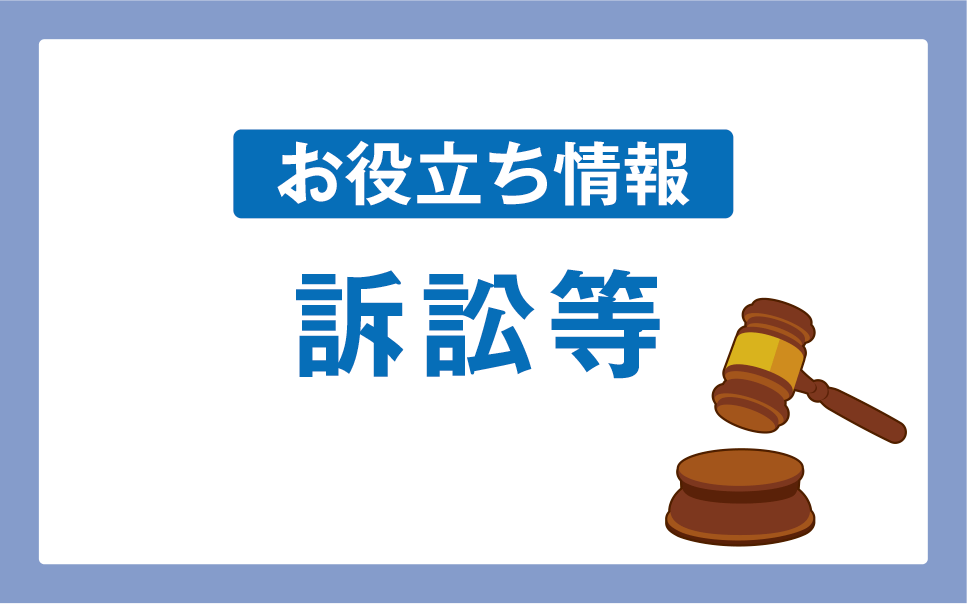自賠責保険による後遺障害が非該当であったところを訴訟により覆した結果、後遺障害部分の補償として約470万円を獲得した事例の経過とは? その2
交通事故の被害事故の法律問題を専門的に対応している千葉の弁護士の大薄です。
前回の続きです。
自賠責保険の後遺障害非該当の判断を覆すために、鑑定医へ医学意見書の作成を依頼することとしたのですが、意見書の作成を依頼するにあたってのポイントとは何でしょうか。
どのような分野でも同じかと思いますが、専門家は専門家同士で会話する際に、話をスムーズに進めるため、業界内における当然の前提を省略してやり取りする傾向にあります。
そのため、当然の前提を省略せずに説明いただくことが重要となります。
医学意見書の作成にあたっては、鑑定医の先生が医学界では当然の前提とされる部分について、説明(論理)や根拠文献を省略する傾向にあることを踏まえて、医学的な素人である法律家(弁護士や裁判官)や依頼者(交通事故の被害者)にも分かりやすく伝わる意見書となるように、鑑定医の先生への質問を重ねて、医学意見書を作成いただきました。
その結果、極めて論理的・説得的な医学意見書を取得することができました。
早速、かかる医学意見書をもとに、自賠責保険への異議申立てを実施したのですが、結果は、まさかの初回申請と同じく非該当で、他覚的所見に基づく後遺障害(12級以上)はおろか、他覚的所見なき後遺障害(14級9号)も認められませんでした。
このような非該当の結果をもとに、今後の進め方について依頼者の方と協議したのですが、依頼者の方に残存する支障や主治医の先生の後遺障害診断書の内容、鑑定医の先生に作成いただいた医学意見書の内容を踏まえると、やはり納得できないとの話になりました。
そこで、訴訟により非該当の結果を覆していく方針としたのですが、後遺障害を獲得する訴訟を円滑に進行させるすべく、訴訟を提起する前に注意したポイントがあります。
それは、どのようなポイントだったのか。
長くなりましたので、続きは次回といたします。